ホーム > news&policies > 「私の視点」 >

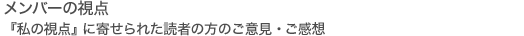
宴のあと 2002年6月22日
自民党の焦燥、『リア王』の孤独
辻本清美さん、田中真紀子さん、所属する政党は違っていても、自民党の長老的・寄り合い政治、腹芸政治に反旗を翻し、可能な限り言語化された、情報の風通しのいい政治環境を目指した点では共通していました。加藤紘一さんは、次期総理候補でしたし、自民党の中では、前近代的なムラ社会的な感覚からはいちばな遠い人のように見えました。鈴木宗男さんについては、自民党的なるものを、いちばん体現しているように見えましたが、彼のような政治手法は、『日本列島改造論』の破綻とともに、時代的な使命を終えたのかもしれません。この「遅れてきた田中角栄」は、自民党にとってもすでに邪魔な存在だったのかもしれないのです。
あとに残る自由民主党という政党のイメージは、泥臭さが抜けて、たしかに紳士的でソフィスケイトされているかもしれませんが、色彩感に乏しく、存在感の希薄な、それでいて、日本という国の津々浦々にまで自分たちの権力のネットワークを隠然と張り巡らし、それでいて、その権力機構なり、ネットワークなりがどんなシステムで動いているのか、といった概略は、あくまで内部の当事者だけが承知をしていて、外部の人間には知らされず、外部からは窺い知ることすらできない、たとえば「学閥」というような言葉で象徴できるような、いかにも日本のエリート好みの、セクト主義に凝り固まった、なんとも薄気味の悪い、茫洋とした政治権力の集合体ではありますまいか。
これが、21世紀的、と言うことでしょうか。
それにしても、この一連の政治スキャンダルに、シナリオを書いた人間がいるとしたら、いったい誰でしょう。自民党内の特定の派閥や、特定の政治家がシナリオを書いた、というよりは、子どもが自分から離反し、独立していく際の、父親の悲しみのようなものが、自民党の個々の政治家をして、このようなシナリオを書かしめたのではないか、と思います。
地元への箱物の利益誘導は、道路も鉄道も橋も空港も、目立つものはすでにやりつくしてしまった。農業政策についても、農産物の内外価格差や狂牛病、食品添加物の問題などで、生産者と消費者との感情的な対立が煽られるだけで、必ずしも農業従事者のための善政がなされるとは限らないことがわかってきた。都市と地方とを問わず、何らかの市民運動、ボランティア活動に参加する人たちが増え、インターネットの普及率はシンガポールや韓国には劣るとしても、「情報開示」や「説明責任」が合言葉になり、有権者の多くは、実質的な言葉を、意味の充填された言葉を求めはじめたのでしょう。
伝統的な家族制度に基づく、穏やかな国家主義を説いても、働く女性たちを白けさせるだけ。ターゲットにしたはずの高齢者たちも、もはや精神的にも経済的にも自立していて、安易に大家族や社会保障に頼ろうとはしない。経済成長に伴う、明るくにぎやかな未来を説こうとしても、本来なら、居住地域や年齢の制約を受けずに高度な教育を受けられたり、物の流通や金銭の流れがシステマチックになることで具体的に豊かさを共有できる、そういう未来像が説かれなければならないはずなのに、土建業や重厚長大産業のイメージしか念頭にないため、明瞭な像を結ばず、リアリティに欠け、説得力を持ちません。
『リア王』に描かれたような、ある意味では愛情にあふれた権威的な父親の、時代に取り残された孤独。それが、自民党に矢継ぎ早に起こった、政治スキャンダルの象徴的な意味ではないか、と思います。(守隨秀章)
関連情報
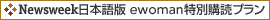


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について