ホーム > news&policies > 「私の視点」 >

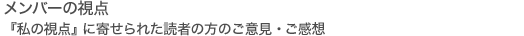
情報の時代に求められるスキル(2003年6月28日)
自分なりの目の高さでいいから、本音でものを考えたい
わたしたちは、今まさに、情報化・情報過・情報禍時代に生きている。全くそのとおりだと思う。情報を操作する力を握った人は、世界をも支配するに違いない。新聞を読み、ラジオを聴き、テレビを見、本を読む。人の話を聞く。インターネットで検索する。確かに、昔よりも情報を得る手段は多い。しかし、同時にわたしたちは考えておかなければならないと思う。わたしたち一人ひとりの時間と手段で得られるのは、あくまでも限られた情報でしかないのだということを。そして最も大事なのは、情報そのものではなく、自分で考えようとする姿勢ではないだろうか。
たとえば、先日、グレート・サスケ岩手県議会議員の覆面問題が取りざたされていた。その裏で例の松浪国会議員の問題は、表面上は忘れ去られていた。問題の軽重は一概に言えないが、国民に対する裏切り行為では、と指摘された松浪議員の問題のほうが大きいはずである。あの問題は最終的にどうなったのか。少なくともメディアのレベルでは解決済みであるかのように見える。あれは、自民対自由の力関係、政治のドタバタ劇であったのか。
世界規模的な例では、自衛隊派遣・北朝鮮の拉致と核開発問題・イラクの大量破壊兵器の有無・日米協調のあり方と、さまざまな情報が乱れ飛ぶ。でも、北朝鮮の現在の状況を報道する画面を見るたびにわたしは思うのだ。きっと、いくつもの戦争の時、日本でもあのように国民は情報操作されていたのだろうと。「鬼畜米英」なんて言ってたのは、ついこの間のこと。そして、今も情報操作されていないとは言いきれない。北朝鮮の脅威を強調されればされるほど、日本人は自衛隊派遣・米国追従(に見えてしまう)にNOが言えなくなっている。もっと大きな観点で、世界の中における日本のあり方を考えたい。でも、脅威の前に身がすくむ。
でも、だからこそわたしたちは、深呼吸をして、しっかりと世界を、時代を見つめ、自分なりの目の高さでいいから本音でものを考えていかなければならないのだと思う。
その際、藤田さんがおっしゃるように、逆の視点でものを見るということは大事である。どんな戦争も「正義・大義」のない戦争は無かったという。一方のものの見方に凝り固まっては見えるものも見えなくなってしまうだろう。
しかし、藤田さんの表現では、「反戦」があるから「戦争をするのも仕方ないときがある」と、違う視点で主張していた。ディベートの練習ならそれでも良いと思うが、あくまで藤田さん個人の考えを述べるコラムであれば、「だからそう主張してみる」ではいけないように思える。反対の視点を提示しつつも、自分の結論を説得力を持って示すべきではないだろうか。揚げ足取りかもしれないし、曲解かもしれないが、藤田さんのコラムの愛読者として、あえて書かせていただいた。
情報はあふれてはいるが限られたものであることを踏まえたい。そして、自分が積み重ねてきた人生から生まれた感性を信じ、多くの学びをもとにその裏づけをする。一人の個人としての意見を持って社会に存在していきたいものである。
自分の判断力を磨くために、常に論理的、かつ違った視点を求めます
藤田さんのコラム、いつも興味深く拝読しております。この度、コラムについて感じたことを書かせていただきます。確かに現在は、大量の情報の海を泳いで行く技術が求められています。一方で、30年くらい前と比べると情報の質も上がっていると思います。その理由として、3つ挙げます。
(1)提供者が増えた分、信憑性の判断もしやすくなった。
昔はテレビ局もあまり多くなく外国のニュースなどは見る機会もありませんでしたし、新聞も購読している紙面以外は目にするのが難しかった。これに対し、今はさまざまなメディアの記事をインターネットはじめさまざまな媒体で入手することができます。ということは、権威のある放送局、もしくは新聞の記事や報道をうのみにする必要がなくなったということではないでしょうか。
(2)情報化社会に慣れてきた。
初めてワープロが登場したときに、自分が打った文章が活字で印刷されてくると、まるで雑誌記者のような気分になったものです。ところが、今や印刷物のみならず、写真や動画をも駆使したホームページなどの情報を世界中に自宅から発信できるようになったのです。最初は、それらの情報を信用していいのか迷いましたが、これだけホームページが一般的になってくると、検索する側にもその情報の信憑性やサイトの質を見極める能力が備わってきたと思うのです。ホームページの自然淘汰も始まっているのではないでしょうか。
(3)情報禍社会は昔からあった。
情報禍ははるか昔からあったのではないでしょうか。原始的な伝達方法である噂話にしても多くの災いをもたらしてきたのではないでしょうか。自らの利益を追求する者が情報操作をしてきたのは昔からのことだと思います。それを考えるとさまざまな考え方を瞬時に検索できる現在は操作された情報に疑問を抱かせるような意見や視点も得ることができるので、自分の判断力が磨かれるのでは、と考えています。
藤田さんのおっしゃる通り、常に論理的な違った視点や反対意見などを提供してくださることが、一市民として優良なメディアのプロに求めることです。
関連情報
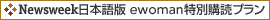


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について