ホーム > news&policies > 「私の視点」 >

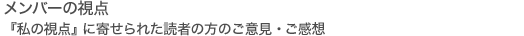
いつまで続ける、この裁判(2004年2月28日)
集中審理の工夫を
オウム関連の裁判はすべて長いと思いますが、長いのは、事件の複雑さのせいだけでしょうか。被告および被告側弁護士がその気になれば、法的にはいくらでも訴訟遅延は可能です。この裁判は、今後導入が予定されている裁判員制度との関係を考えても興味深い事例ではないでしょうか。被告の人権ばかりが強調されがちですが、原告の人権や、社会全体の問題を考えたとき、集中審理の工夫をしていかないと、この種の裁判に参加するかもしれない裁判員も大変なことになると思います。
それにしても、破防法の適用もなく、単にオウム(現アーレフ)を監視しているだけの日本の現状は、あまりにもおかしいと思います。数千人に被害を与えても、個人の処罰しかないようでは、日本はテロリストにとって、ある種の楽園と映るのではないかということを懸念します。(A6M2)
なぜテロを行うようになったのか
藤田さんは麻原のような人物に人権を保障するのは疑問があるという考えでいらっしゃると受け止めました。しかし、制度を悪用して自己の権利のみを主張するのは麻原だけではないと思います。問題は、オウム(現アーレフ)のような、本来はマイナーな集団が、なぜ勢力を拡大し、テロを行うようになったのかということではないでしょうか。裁判を通じてその辺の事実関係があぶり出される可能性があるなら、この裁判には、テロ集団の責任者の処罰という以上の大きな意味があると思います。
オウム(アーレフ)には、いつのころからかわかりませんが、カルトとは別な要素があると思います。だから、警察の公安も内偵していたのではないでしょうか。また、あれだけのテロをやって、なぜ破防法の適用が見送られたのでしょうか。どうして国会はカルト集団規制法を立法しようとしないのでしょうか。麻原裁判の見方は、もっと多面的に論じていく必要があると思います。(匿名)
世間一般から見れば、やはり長い
わが子が生まれたちょうど一週間後に地下鉄サリン事件が起きました。その子ももうすぐ小学4年生。たしかに事件の大きさからみれば短いのかもしれませんが、世間一般から見れば、やはり長いと感じるのではないでしょうか?
冤罪でないことはたしかで、死刑になることも確実だから、さっさと死刑判決を確定して刑を執行してしまえばいい……ということでは済まないところに、裁判の難しさを感じます。なぜこのような事件が起きたのか、大量の人を殺してまで欲しかったものは何なのか、真相究明に少しでも迫ってもらいたいと思います。(いまいくん)


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について