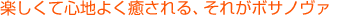

ボサノヴァは、58年に広まったんです。ジョアン・ジルベルトさんという、ギタリストでもあり、歌手でもある人が中心となって創ったスタイル。ギターのバッキングとハーモニーとか、新しい和音のパターンやコード進行、半音階を多く使ったメロディー、抑えたボーカル、いろんな新しい特長が生み出されました。当時ブラジルでは、朗々と歌い上げる懐メロみたいな音楽と、黒人の音楽としてのサンバが主流だったんですけど。その両方を合わせて一つにして、シンプルにそぎ落として洗練させていったんですね。ボサノヴァという名前は、ボサが「傾向」、ノヴァが「新しい」という意味で、フランスのヌーヴェルバーグみたいな新しいムーブメントにしたかったんだと思います。自分達はもっとクールな音楽をやりたい、失恋の歌ばかり歌っていたくないと思った中流階級の大学生や若者たちに受け入れられたようです。
 ボサノヴァの特長の一つは、メロディーが動かないことなんですね。「ワンノートサンバ」という曲がありますけど、ワンノートいうぐらいメロディーがずっと同音で続く。でも、そのハーモニーが変わっていくんです。低音が半音ずつ上がったり下がったりして、その音が加わって動いていくというか……。言葉で説明するのは難しいけど、聴いていただければわかると思います。ボサノヴァの心地よさの源泉は、抑揚があまりないメロディーにあるのかもしれません。お経みたいですね(笑)。
ボサノヴァの特長の一つは、メロディーが動かないことなんですね。「ワンノートサンバ」という曲がありますけど、ワンノートいうぐらいメロディーがずっと同音で続く。でも、そのハーモニーが変わっていくんです。低音が半音ずつ上がったり下がったりして、その音が加わって動いていくというか……。言葉で説明するのは難しいけど、聴いていただければわかると思います。ボサノヴァの心地よさの源泉は、抑揚があまりないメロディーにあるのかもしれません。お経みたいですね(笑)。
わたしにとってのボサノヴァは、ふるさとの音楽でもあるし、楽しいだけでなく癒される。自分の性格とか生活スタイルにすごく合っているんだと思います。静かでおとなしくて(笑)、それで楽しいところもあるし。日本に帰って来た10歳位のころはいつも、ジョアン・ジルベルトさんやアントニオ・カルロス・ジョビンさんなど、ブラジルのアーティストの音楽を聴いてました。ベランダにハンモックを吊って。
このリポートを読まれて、感じたこと、考えたことをぜひ教えてください。あなたのご意見をお待ちしています。
 投稿する
投稿する


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について