ホーム > news &policies > 規制改革メルマガ

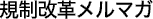
保育や学童は、福祉か否か?
2001年7月25日(水)配信
創刊号を読んで、ご意見をくださったみなさん。どうもありがとうございました。
早速、昨日の「総合規制改革会議」で、規制改革担当大臣の石原のぶてる氏に、わたしが直接、みなさんの意見をプリントして提出してきました。お読みいただけると思います。
予告では、今回は「認可基準」についてディスカッションする予定でしたが、大きな問題を提起している読者の方の投稿がありましたので、それを議論の材料にしていきます。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
保育や学童は、福祉か否か?
- A:
びっくりするような投稿があったということですけど、どんな投稿があったの?
- B:
ええ、これを読んでみてください。
大田区の認可保育園に5歳(年長)の娘を預けています。
来年から小学校で学童保育に入れようと思っているのですが、先日その資料として父母の会から配られた「大田区学童保育指導要領」の中に、びっくりする表現がありました。
「指導上の基本的要件」の「家庭的ふん囲気と暖かい環境の醸成」の項に、こう書いてあります。 「学童保育所に通う児童は、日中家庭から放置され、正常な生活の場と保護者の適切な看護や十分な愛情をえられないため、それによっておこるさまざまな欲求不満から、不健全な遊びや反社会的な行為に走りやすい。またこのような状態が継続することによって情緒不安や孤独癖に陥り、あるいは放浪性や活動過多症(落つきのなさ)を呈するなど、その人格の形成の上でも好ましくない影響を生ずることが少なくない」
だから、家庭的なふん囲気が必要だ……ということなのですが、「家庭から放置され」ているわけでもないし、「十分な愛情を得られない」ということでもないと思います。区をはじめとし、国や自治体の考え方が、現状と大きく食い違っていることを知り、怒りを感じるとともに、情けなくもなってしまいました。(Lisa)
- A:
ひどい断定ね。母親が仕事をしているは不良になりやすい、と言ってるようなものだわ。でも、なぜこんな表現が許されるのかしら? 大田区児童部がオリジナルに考えた表現なの?
- B:
わたしもびっくりして調べてみたんですが、これは東京都がかつて使っていた「学童保育指導要領」なんです。でも、現在はこの指導要領は廃止されています。ですから、事実としては、大田区が廃止された指導要領をいまだに使っている、ということなんです。
- A:
指導要領の文言は変わっても、現実面で、「学童保育」に対する考え方は変わってないってことの表れ?
- B:
ええ。「保育」に関することなので、厚生労働省の文書にある文言かなとも思ったんですよ。
- A:
どうして?
- B:
-
「学童保育」はお役所の言葉で言えば、「放課後児童健全育成事業」と言うんですけど、この事業を管轄しているのは、厚生労働省なんです。
- A:
たしか「保育所」も厚生労働省の管轄では?
- B:
そう。保育所や託児所・学童保育は厚生労働省。幼稚園・小学校は文部科学省が、それぞれ管轄しています。依拠している法律も、それぞれ「児童福祉法」と「学校教育法」というふうに、別々なんですよ。そこでぜひとも知ってもらいたいのは、両者の目的の違い。簡潔に言うと、保育所の目的は、「保育に欠ける」乳幼児・児童の保育となっています。一方、幼稚園は、就学前の準備教育を主たる目的としています。
- A:
保育や学童保育が厚生労働省の管轄ということはわかったわ。でも、それと、さっきのひどい表現とは、どういう関係があるの?
- B:
つまり、「保育所」や「学童保育」は、「福祉」として考えられ進められてきているから、厚生労働省が管轄しているということ。だから、「家庭から放置され」とか「保育に欠ける」という表現が、基本にあるようなのです。
- A:
そうか! 「福祉」という言葉には、ある水準の生活状態に達していない、というニュアンスが含まれるのね。
- B:
まだ日本が貧しかったころは、夫は外で働き、妻は家でを育てる、というのが典型的な家庭像でした。そんな時代なら、妻が外に働きに出ることが、 「夫の稼ぎだけでは生活していけない、それゆえ、子育てができない」という考え方になるのは、やむをえない面があったかもしれない。そういう家庭に対する「福祉」として、言葉を換えれば「救済措置」として、政府は公的資金をたくさん使って公立の保育所を作ったんです。児童福祉法は改正され、大田区が配布したような文言は消えたようですが、現在でも「保育に欠ける」のための施設、ということは基本です。でもいま、保育所にを預けたいお母さんを、いっしょくたにして「保育に欠ける」というのは、とてもナンセンスだと思うんです。だって、金銭的余裕はあっても、自分で選んで働いたり、仕事に生きがいを見出す女性だって大勢いるんだし。
- A:
保育所や学童保育に求めるニーズも多様になってるからね。そうなると、保育所や学童保育を「福祉」としてのみ見ることに、限界があるのかも。
- B:
ええ。わたしたちが「待機児童ゼロ」を支援したり、「保育施設がほしい」と発言することは、必ずしも「文部科学省の管轄ではなくて、厚生労働省の考えにも とづいて保育施設を増やしてほしい」ということを言っているとは限りませんよね。幼稚園と同じような「教育」のニーズを、保育所に求める声だってあるし、昨日までのみなさんからのご意見にもすでにあるように、多様な施設を望んでいる。わたしも、保育や学童保育のすべてを「福祉」と定義づけるのは、そろそろ限界ではないかと考えるんです。幼稚園や小学校もあわせて仕切り直す必要があると思うんですが。
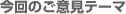
「保育や学童は、今後も福祉としてとらえ、進めるべきでしょうか?」

 総合規制改革会議 総合規制改革会議
「議事内容」に、これまでの総合規制改革会議でどんな議論をしたかが書かれています。
 全国学童保育連絡協議会 全国学童保育連絡協議会
 規制改革担当大臣の石原のぶてる氏 規制改革担当大臣の石原のぶてる氏
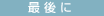
事実と違う! とか、実態を知らないのでは! もっと根が深い!といった意見も、是非お寄せください。
ただ、ご意見をいただく際にお願いしたいのは、「たち」にとって一番よい環境を作るために、いままでの既成概念を捨てて、新しく考えること、そして違う意見にも耳を傾けて、前向きに、建設的に話し合うことです。
このメルマガは毎週水曜日に発行し、同じ週の金曜日に、みなさんからのご意見をewomanサイトで掲載します。それを読んで、また続けてご意見いただければと思います。
サイトへの掲載をするか否か、編集権、2次使用権はewomanに帰属することをお許しください。個人名を書いていただきますが、サイト掲載または2次使用の際は、個人名ではなくewomanニックネームを掲載させていただくことでみなさんのプライバシーを守りたいと思います。いただいたご意見は、サイトに掲載されない分も含めて、すべて佐々木が内閣府に届け、届けたことをサイトにてご報告いたします。批判ではなく、改革。
建設的に、意見を積み上げられたら、と思います。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について