ホーム > news &policies > 規制改革メルマガ

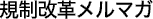
保育を「厚生労働省」だけに任せていいの?
2001年8月1日(水)配信
創刊号に引き続き、たくさんの投稿ありがとうございます。それぞれのご意見が、非常にポイントを明確にしていてわかりやすく、みなさんの真剣さが伝わってきます。 先週のメルマガに対しては賛成と反対、意見が割れ、わたしも考えさせられました。
とても反響の大きいテーマでしたので、今回、もう一度、みなさんの投稿を紹介しながら、議論を深めてみたいと思います。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
保育を「厚生労働省」だけに任せていいの?
- A:
前回のメルマガ、大反響だったみたいね。「保育や学童を今後も『福祉』として進めるべきか?」という質問だったよね。
賛成と反対、どのくらいの割合だったの?
- B:
賛成が27.5%、反対が62.5%でした。わたしなりに投稿を整理してみたんですが、まず反対の人たち、つまり保育や学童は「福祉」に限定してとらえるべきではない、という人たちは、わたしとほぼ同じ意見の持ち主です。
一方、「保育=福祉」に賛成という人たち、これは大きく分けると二種類の意見にわかれました。一つは、従来の厚生労働省的な「福祉」のままでよい、という意見。これは、全体の10%ぐらいです。もう一つは、自分なりに「福祉」という言葉を再定義して、それに沿うものとして「保育」をとらえる意見です。こうした意見が全体の約17%でした。
- A:
あなたの質問の真意はどんなところにあったの?
- B:
わたしの質問の意図は、今後も「厚生労働省」のみに「保育」を任せる、という方向を支持するかどうか? というものです。ですから、賛成とした中の後者の人たちとは、決して立場は対立していないと思うんです。
- A:
それはどういうこと?
- B:
たとえば、賛成と書いているDulcianさんは、「福祉」を「理想的な人間生活を目指す」ために必要なものと定義した上で、核家族では難しい「人間性や社会性を育てる」場所として、保育所を考えたらどうか、と提案しています。
- A:
いい提案だと思うけど。
- B:
ええ。だからこそわたしはさらに「そういう保育所は、厚生労働省の管轄じゃなければいけませんか?」と尋ねたいんです。同じく賛成としているkeroyonさん は、厚生労働省的な「福祉」の概念は誤ったとらえ方だけど、保育や学童に関連する施策の進め方は「セーフティ・ネット」と考えるべき、と書いています。
- A:
なるほど、二人とも自分の考える「福祉」に沿う保育所であれば、厚生労働省が管轄しなくてもいい、と思っているかもしれないものね。
- B:
そう。別の言い方をすれば、それぞれが抱いている「福祉」のイメージは、十人十色なんです。これはそのまま「保育」に求めるニーズについてもあてはまる。 だとしたら、なおさら厚生労働省のみに「保育」を任せる必要はないと思うんです。
- A:
あなたと同じく反対の人は、どんな意見を書いてきたの?
- B:
オラシオンさんは、「幼稚園に延長保育が導入されるように、保育園にも教育を盛り込むことはおかしくないと思う。幼稚園と保育所の中間みたいなものがもっとあっていいのかもしれないと思う」とズバリ書いています。そして、そういう場を作るには、「福祉という考え方から脱しなければありえない」とも。これは、いずれ大きなテーマとして扱いたいと思っていますが、「保育所」と「幼稚園」の融合を進めてほしい、という提案とわたしは受け取っています。
もうひとつ鋭いと思ったのは、「保育園のいいところは、早くから社会の一員としての自覚を持つことだと思います。・・・社会全体が、を保護すべき存在ではなく、社会の担い手として考えていくことが重要なのではないでしょうか」と書いてきてくれたstomoさんの意見です。これは、保育所の役割は家庭の代替機能だけではない、ということです。
- A:
説得力あるわね。「保育に欠ける」児童を対象にするという厚生労働省の従来の考え方からすれば、保育所は家庭と同じことしかできない、ってことになるものね。でも現実は、家庭とは違う役割を担っている部分があるもの。
- B:
そして面白いことに、先ほど紹介した賛成派のDulcianさんも、反対派のstomoさんも、保育所を「社会性を育てる」場所ととらえる点では一致しているんです。
やや強引なまとめかもしれませんが、保育所に、幼稚園と同じような「教育」を求めたり、家庭だけでは限界のある「社会性の自覚」を求めたりするのであれば、「保育=厚生労働省の管轄のみ」という枠組み自体を検討する必要があるのではないでしょうか。
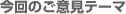
「保育や学童を、今後も厚生労働省だけに任せることを支持しますか?」

 総合規制改革会議 総合規制改革会議
2001年7月24日に提出された中間とりまとめを読むことができます。
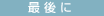
事実と違う! とか、実態を知らないのでは! もっと根が深い!といった意見も、是非お寄せください。
ただ、ご意見をいただく際にお願いしたいのは、「たち」にとって一番よい環境を作るために、いままでの既成概念を捨てて、新しく考えること、そして違う意見にも耳を傾けて、前向きに、建設的に話し合うことです。
このメルマガは毎週水曜日に発行し、同じ週の金曜日に、みなさんからのご意見をewomanサイトで掲載します。それを読んで、また続けてご意見いただければと思います。
サイトへの掲載をするか否か、編集権、2次使用権はewomanに帰属することをお許しください。個人名を書いていただきますが、サイト掲載または2次使用の際は、個人名ではなくewomanニックネームを掲載させていただくことでみなさんのプライバシーを守りたいと思います。いただいたご意見は、サイトに掲載されない分も含めて、すべて佐々木が内閣府に届け、届けたことをサイトにてご報告いたします。批判ではなく、改革。
建設的に、意見を積み上げられたら、と思います。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について