ホーム > news &policies > 規制改革メルマガ

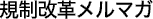
規制改革メルマガ終刊にあたって
2001年10月24日(水)配信
今回で、3ヶ月間のメルマガ、最終回となりました。たくさんのご意見、すべてを内閣府に届けました。担当の石原大臣だけでなく、明日は森前首相にもお届けします。
ewomanは、生活しているわたしたちの声を一つにして、企業や社会、政府に伝え、変化を起こしていきます。 これからもみなさんと一緒に考え、進んでいきたいと思います。ありがとうございました。
ewoman:規制改革メルマガ編集長
佐々木かをり
規制改革メルマガ終刊にあたって
- A:
最初は500人ぐらいだったメルマガの読者が、今では2000人を超えたそうね。今回で終えるのは、ちょっと残念な気がする。
- B:
そうですね。硬派なテーマであるにもかかわらず、大勢の方に読んでいただくことができ嬉しく思いました。それに人数だけでなく、投稿いただく内容の質の高さ、奥の深さに毎回勉強させていただきました。
わたしがみなさんに伝えられたことよりも、学ばせていただいたことのほうが大きかったんじゃないかと思っています。
- A:
そもそも、このメルマガを出すことになったのは、あなたが総合規制改革会議のメンバーの一人になったことが発端よね。会議に出てどんなことを感じた?
- B:
言い始めるとキリがないんですが、社会の見方は、相変わらず男性の視点が中心なんだな、ってことです。政治も経済もメディアも、男性が「長」として仕切っていることが圧倒的に多い。女性誌の編集長も男性が多いですよね。その結果どうなるかというと、生活者の実感がすくいとられないまま話が進んでしまって、決定されていくことが多いんです。
- A:
なるほど。保育所の「民営化」の話もその一つかもね。「民営化」だけが話としてどんどん進んでしまって、そのために起こり得る負の部分──営利が優先されてしまったり、保育士の質が低下したり──を忘れがちになっているもの。
- B:
-
だからわたしが会議に参加するにあたっては、「生活に密着したわかりやすい改革」にしていきたいと思ったんです。ただ、そうは言っても、自分が考えていることがベストとは限らない。そこで、自分だけの思いにとどまらず、このメルマガを通じて、いろいろな方々の意見を聞くことができたら、と思ったわけです。
また、お役所の言葉遣いには相変わらず悩まされます。中間とりまとめを読むとわかるんですが、文末はたいてい「〜べきである」で終わっているんです。さらに「主語」がほとんどありません。
- A:
お役所の暗黙の了解なのかしら。意地悪な見方をすれば、「べきである」って、「しないこともありえる」ってことだし。
- B:
そう。話が脇にそれるので、このへんにしておきますが、言葉遣いに関しては、ときどき自分の理解力が低いのかな、と不安になるくらいです(笑)。
- A:
ところで、改革はうまくいきそうなの?
- B:
いま石原大臣は、規制改革項目を前倒しして実施することを主張しています。たとえば「平成14年中に実施」を「平成13年中に実施」という具合に、一年前倒しして改革のスピードを速めようとしています。年末には閣議決定があり、そこでどれだけのことが決められるか、にかかっています。
うまくいくかどうかは、現状では断言できません。思った以上に、わたしでも感じる抵抗勢力の声が強くあるんですよね。極論を言えば、小泉首相や石原大臣がやろうとしている「改革」や「変化」を一番強くサポートしているのは、世論だと思うんです。
中身については議論の余地があるにせよ、わたしは、既得権益やいまの地位に甘んじている人ではなく、小泉首相の「社会を変えたい」という姿勢に共鳴するし、応援したいと思っています。
- A:
このメルマガはまた再開するの?
- B:
定期的に出す予定はいまのところありませんが、議論したいこと、みなさんの意見を聞きたいことは、出てくると思うんです。そんなときには、特別号として配信する予定です。前号で話題にした「第三者評価サイト」が具体化したときには、あらためてお知らせします。
バックナンバーのご意見は、随時受け付けていますし、こんなことを考えてほしい、という投稿も大歓迎です。
今後もぜひ「わたしたちの改革」を一緒に考えてください。
そして最後に、以下のわたしの宿題を手伝っていただける方、お待ちしております。
3ヶ月という短い間でしたが、どうもありがとうございました。
<番外編>
総合規制改革会議のワーキンググループで、以下の内容について発表することになっています。もし、ぜひとも伝えてほしい意見や情報などがあれば、お知らせください。特に「2」や「6」で、有益な情報があれば教えていただけると助かります。
【議題】 教員の資質向上(企業経験者の積極的採用、教員の企業研修等、の学校カウンセラー等専門家へのアクセス)
【発表内容】
- 1.現状分析
- −現在生じている問題点は何か。
- −問題点と規制の存在の因果関係。
- 2.規制の状況
- −現在の規制は、どのような法令(法律、政令、省令、その他)や制度か。
- 3.具体的な改革案
- −現在の規制を、どのように改革していくべきか。複数のオプションと、 それぞれについてのメリット・デメリット分析。
- −規制改革を実現することにより期待される効果は何か。
- 4.規制改革の必要性
- −経済社会構造の変化など、従来の規制体系を改革する契機。
- 5.予想される反論と再反論
- −規制を改革することについて、逆の立場をとる関係省庁、団体等から予想 される反論はどのようなものか。
- −また、このような反論に対しては、どのように再反論するか。
- 6.(参考資料)諸外国の状況
- −現在の規制について、諸外国ではどのような規制体系を有しているか。
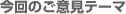
「保育・学校、ココを改革してほしい」

 総合規制改革会議 総合規制改革会議
2001年7月24日に提出された中間とりまとめを読むことができます。
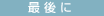
事実と違う! とか、実態を知らないのでは! もっと根が深い!といった意見も、是非お寄せください。
ただ、ご意見をいただく際にお願いしたいのは、「たち」にとって一番よい環境を作るために、いままでの既成概念を捨てて、新しく考えること、そして違う意見にも耳を傾けて、前向きに、建設的に話し合うことです。
このメルマガは毎週水曜日に発行し、同じ週の金曜日に、みなさんからのご意見をewomanサイトで掲載します。それを読んで、また続けてご意見いただければと思います。
サイトへの掲載をするか否か、編集権、2次使用権はewomanに帰属することをお許しください。個人名を書いていただきますが、サイト掲載または2次使用の際は、個人名ではなくewomanニックネームを掲載させていただくことでみなさんのプライバシーを守りたいと思います。いただいたご意見は、サイトに掲載されない分も含めて、すべて佐々木が内閣府に届け、届けたことをサイトにてご報告いたします。批判ではなく、改革。
建設的に、意見を積み上げられたら、と思います。
|

|
|


 >>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について
>>> 旧リーダーズ/メンバーからの移行登録について